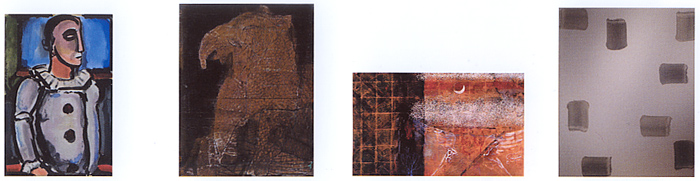 |
『流れる星のサーカス“ピエロ”』
ジョルジュ・ルオー
この作品は、私が特に好きな一点である。ルオーは“人間は道化師、自分も道化師”と語り、道化師を主題にした作品を生涯に亘ってたくさん描いている。このピエロは華やかなサーカスのステージから降り、ふと自分に戻った時の“人間としてのピエロ”である。悲しそうな目をしているが、よく見るとルオーの人間に対する優しい視線が滲んでいる。 |
|
『獏(ばく)』
岡村桂三郎
新たな日本画の世界に挑戦する岡村桂三郎、近年は龍などを主題にしたスケールの大きい屏風絵に取り組んでいる。木目の浮き出たボードを焼け焦がし、洗い流し、下地を作った上に墨と岩絵の具で描き、削り、かつ描くという新たな表現を確立しつつある。この作品もその一つ。描かれているのは夢を食うと言う中国の想像上の動物“獏”である。 |
|
『贖いのふた』
マコト フジムラ
『贖いのふた』とは旧約聖書の出エジプト記に出てくる神との契約の箱のことである。贖いとは神による人間の罪の贖い。贖いのふたとはキリストを意味している。これは1992年の東京芸大博士課程終了展出品作である。天使の翼に包まれるように少年像が描かれ、金箔の上の緑青や辰砂、金泥など岩絵の具の深い色合いが、神聖な美しさを放っている。 |
|
『照応 Correspondence』
リ・ウーハン(李 禹煥)
リ・ウーハンは60年代以降、もの派の中核的存在として活躍してきた。代表作の「線より」「点より」など、余計なものを削ぎ落とした清潔で透明感溢れる世界だ。“余白の芸術”について「制作することにおいては最小限でありながら最大限の交感をもたらすもの」と語っているが、作品とそれを取り巻く全体の空気を余白として捉えた宇宙観である。 |
|
 |
『大威徳明王』
松田正平
松田正平の絵は枯れた具象の世界。周防灘など、そのフォルムや即興的な線のなんと軽妙で洒脱なことか。そこにあるのは日本人の心の風景そのものである。本作品は作家が好んで描いた大威徳明王であるが、憤怒の相の明王も神性を備えるという臥牛も、おおらかでユーモアある表現となるから不思議だ。まさに即身成仏の境地で描いた作品に違いない。 |
|
『静物画 オリーブ油差し、陶器の瓶、木匙』
早川俊二
30数年前パリに渡り国立美術学校でデッサンから学び直した早川俊二。自ら作り上げた独自の絵の具による辛抱強い姿勢から生み出された画風は、堅牢で重厚な絵肌の独特の世界だ。描く対象は機械油差しやコーヒー挽き、リンゴや梨など身近なもの。あるいは女性像である。この作品はオリーブ油差しなどが描かれているが、深みのある画風が美しい。 |
|
『黒い魚』
半田強
反骨と自由への憧れ。そして無常観に生きる作家がいる。青春時代に志のため放浪の旅に出たという人生行路の果てに結実した作品が今ここにある。褐色の大地や人間、黒い魚や動物などを諧謔的ユーモアをもって描いているが、表面的な美しさではなく、醜くは見えても天地のあらゆるものに内在する根源的な美に迫ろうとする姿勢は宗教的ですらある。 |
|
『Work』
山田正亮
山田正亮は敗戦と戦後の混沌の時代に多感な青春を生きた世代であり、その精神的な彷徨の中から生み出された作品群は、深い精神性と哲学的な魅力を漂わせている。特に60年代のストライプシリーズは、その代表的作品である。横縞の線の反復による作品は無機質な印象を与えるが、よく見ると決して単純な線ではなく、作家の手による人間性が滲んでいる。 |
|
 |
『無の果てに』
山内龍雄
ここに孤高の作家が一人いる。北海道厚岸の酷寒の原野に佇む貧しい住処で、祈るように作品と向きあい、日が暮れればキャンバスと抱きあって寝るのだという。限界ぎりぎりまで薄く削るという気の遠くなる作業から生まれたキャンバスの上の色彩は透明感に溢れ、深い美しさを放っている。どこまでも削ぎ落した末の静寂がここにある。 |
|
『森の扉』
野坂徹夫
野坂徹夫はチェロ奏者でもあり、心に沁みる詩も書く。そんな作家が生み出す作品には詩があり、いまにも音楽が聴こえるようだ。薄塗りの水彩を幾重にも重ねた作品は、透明感ある淡い色調がどこまでも美しい。描かれるのは父と子、愛し合う二人など簡潔なフォルムの人のかたち。そのどれにも祈りが込められており、見る人を感動させる。 |
|
『歩く人』
三浦逸雄
三浦逸雄の作品は、人物が静かに佇むか腰かけているといった室内風景が多い。どれも素っ気ないほど単純な構図だが、その内面化された空間表現が素晴らしい。この作品は男が一人、まっすぐな道を今歩みだそうとする情景である。遠くには薄雲も湧いて平坦とばかりは言えない道程だが、淡い光に包まれた空気は希望ある未来をも予感させる。 |
|
『マリオネット』
岸田淳平
岸田淳平の作品はそのフォルムと洒脱な線が実にいい。テーマは人間である。特に愁いを含んだ女たちを描かせたら右に出る者はいないのではなかろうか。墨や染料、岩絵の具を駆使しての表現は滲んだ色彩が渋く美しい。この作家の作品が観る者の心に沁みるのは、描写力だけではなく、作家の根底に流れる人間への優しさによるものに違いない。 |
|
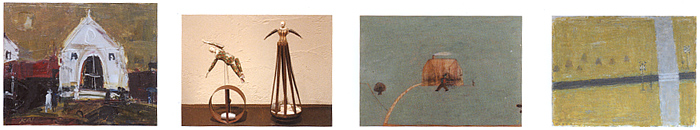 |
『パリ風景』
横田海
男のロマンが匂い立つような横田海の世界、やさしい作品が多い時代にあって稀有な存在である。緻密な画面構成、重厚な色彩と激しい筆触、躊躇いのない線、しかも時に繊細な内面表現。私は円熟などとは無縁に見えるこの作家が好きである。男の純情という言葉がよく似あう。無頼に見えながら無垢な少年の如き生き方は、山頭火を思わせる。 |
|
『変わりやすい気分』
『いつも気になること』
前田昌良
前田昌良の作品を初めて見た時、一気に引かれた簡潔な線や煙るような繊細な線などデッサン力に魅かれたが、抽象作品も濃淡ある色彩と線との調和が知的な雰囲気を漂わせて見応えある。しかし、楽しいのは積み木や西洋骨董玩具のような立体である。作家の遊び心と記憶の中から生まれた作品はいずれも魅力的で、小さな宇宙をかたち作っている。 |
|
『青い空に白い煙』
平澤重信
過ぎ去りしものたちへの郷愁。ここにこの作家の作品の魅力がある。登場するのは白い煙が立ちのぼる煙突のある家、自転車を走らせる少年、庭の小さな木や鳥や犬、家に向かう細い道、しかも時刻は夕暮れ。これは我々の記憶のなかの心の風景そのものだ。特にこの作品は、余白の画面構成、デフォルメされた形、抑制の利いた色彩が実にいい。 |
|
『田圃のなかの踏切』
森本秀樹
森本秀樹の描く宇和島の風景はどれも心に残る。街並みのくすんだ白壁や波止場の釣り人、操車場跡の静寂などが抑えた色調で描かれ、懐かしいものに出会った時のようなしみじみした気持にさせられる。この作品は田圃のなかの踏切を描いているが、信号機や積穂は手前からの視線、縦に走る田舎道は俯瞰の形になっていて、その構図が心地よい。 |
| ※作品紹介文は山下透 |
|